現在の精華町、木津川と西方に連なる丘陵の間には数万年前から人々が住み、紀元前3~2世紀になると稲作も盛んになりました。3~4世紀には有力な地域の首長も現れ、4世紀後半からは精華町内でも次々と古墳が築かれていきます。古墳時代、現在の奈良盆地や大阪平野で、倭国の首長を中心として有力氏族が連合して成立したのがヤマト王権です。そして、ヤマトに反旗を翻したのが、久須婆(大阪府枚方市樟葉)を拠点にしていた第8代孝元天皇の皇子・建波爾安王でした。
『古事記』によると、第10代崇神天皇の時代、蜂起した建波爾安王が、朝廷の軍勢と木津川を挟んで激突したものの、建波爾安王は矢に射られて戦死してしまいます。逃げる敗軍も次々と切り殺された ―という説話が「波布理曽能」という地名になったといいます。『日本書紀』でも、武埴安彦の反乱として同様の逸話があり、「羽振苑」という地名の由来が語られています。日本書紀では古い時代の物語として描かれていますが、実際には4世紀末ごろの出来事と言われています。
非業の死を遂げた武埴安彦の亡魂は鬼神となり、この地にとどまりました。悩んだ人々は春日大明神を勧請して社を建て、神事を執行して鎮魂しました。これが祝園神社、そして「居籠祭」の始まりといいます。


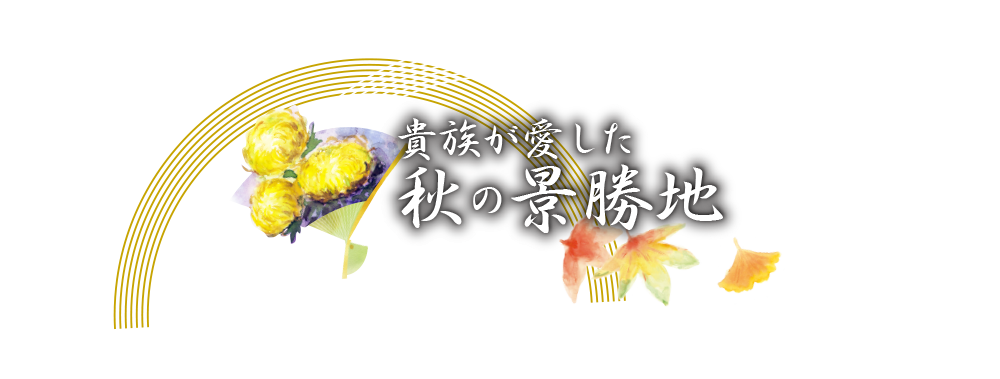
時代は下がって、平安・鎌倉時代、祝園は再び、史料に頻繁に登場します。春日参詣の中継地として貴族たちの日記に綴られ、紅葉の名所として和歌に詠まれるのです。
奈良・平城京の東に位置する春日社は藤原氏の氏神です。10世紀に摂関家・藤原氏の勢力が増すと、平安京から祭使が送られ、貴族も盛んに春日社へ参詣しました。都からの参詣道のひとつが泉河と呼ばれた木津川を舟でさかのぼったり、左岸を徒歩で進んだりするルートです。春日社に加えて、高野山や吉野への参詣も精華町を経由しました。例えば、永保元(1081)年には白河天皇、永長2(1097)年には堀河天皇、天永2(1111)年には少年だった鳥羽天皇も祝園を経由して南都行幸しています。天皇が乗る鳳輦や牛車、騎馬の公卿らが壮麗な列をなし、南都へ、そして帰路、都を目指しました。祝園の南には食事をとる休憩所が設けられ、一行はしばし旅の足を休めました。
貴族たちは特に、木津川の舟旅を愛したようです。
著名な歌人・藤原定家は、建仁2(1202)年の春日詣を詳しく日記に残しています。出仕後に鳥羽から乗船、宇治川あたりで舟をとめてひと眠り。夜明け前から木津川をさかのぼり、泉木津で馬に乗り換え、奈良へ。春日社に参った後は、終夜、木津川を下り帰路についた、とあります。定家は翌年にも摂関家の一行から抜け出し、木津川でのひとときを楽しんでいます。
川面を渡る風に吹かれてのんびりと行く舟旅は創作意欲を大いに刺激したのでしょう。柞、つまりコナラやクヌギなど色づく広葉樹に彩られた祝園一帯は、紅葉の景勝地として歌枕になりました。
時わかぬ浪さへ色にいづみ河
はゝその杜に嵐吹らし
季節によって違うはずのない木津川の波さえも嵐に散った柞の紅葉で色づくようだ・・というところでしょうか。この歌は『新古今和歌集』に収められています。新古今和歌集より前に選集された『千載和歌集』にある賀茂成保の歌も秋の見事さを伝えています。
吹きみだる ははそが原をみわたせば
色なき風も紅葉しにけり
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に登場した鎌倉幕府三代将軍・源実朝は、定家に師事した優れた歌人としても知られます。『金槐和歌集』にも、祝園に思いをはせた歌があります。
泉川 はゝその杜になく蝉の
こゑのすめるは夏のふかさか
御家人の謀叛や権力闘争に心を痛めつつ、京の都の文化や暮らしにあこがれ続けた若将軍が、師の愛した木津川の舟旅への憧れを歌ったのでしょうか。
氏子が誇る祝園の居籠祭
武埴安彦の魂をなぐさめ、豊作を祈る「居籠祭」は毎年、年明け最初の申の日(申が月3回の場合は2度目の日)から3日間営まれます。祭りは1日目、厳かな秘儀「風呂井の儀」で始まります。2日目の「御田の儀」で掲げるのは、1か月ほど前に氏子たちが作った長さ12尺(約4m) 、 重さ約100キロの大松明。闇の中、「もうでござい」の声が掛かると集まった参詣者も静粛に、祭場「幸の森」へ向かう松明を見守ります。五穀豊穣を祈る神事後の直会では、トウガラシや豆腐の入った名物の郷土食「豆腐汁」で体を温めるそうです。
3日目は「綱曳の儀」。こどもたちも参加して 、わら束を竹皮で巻いた輪に付けた青竹を引き合います。神事が終わると竹は神社南の「出森」まで運び 、 焚き上げます 。 ここは武埴安彦が斬られた場所と伝わり 、 現在でも「武埴安彦破斬旧跡」という石碑が建っています。
地域の誇りである祭りは、京都府指定無形民俗文化財に指定されています。

祝園神社いごもり祭保存会
喜多 俊夫 会長(64)
祝園神社いごもり祭保存会の喜多俊夫会長は「かつては会話はもちろん、できるだけ音をたてずに家に籠り、奉仕しました。遠方からの参詣も多く、今でも手を合わせて松明の火の粉を受けておられる姿に触れると、厳かな気持ちになります。新型コロナウイルス感染症の影響で2年間は神事のみの縮小催行になりましたが、来年こそは」と祈りを込めています。


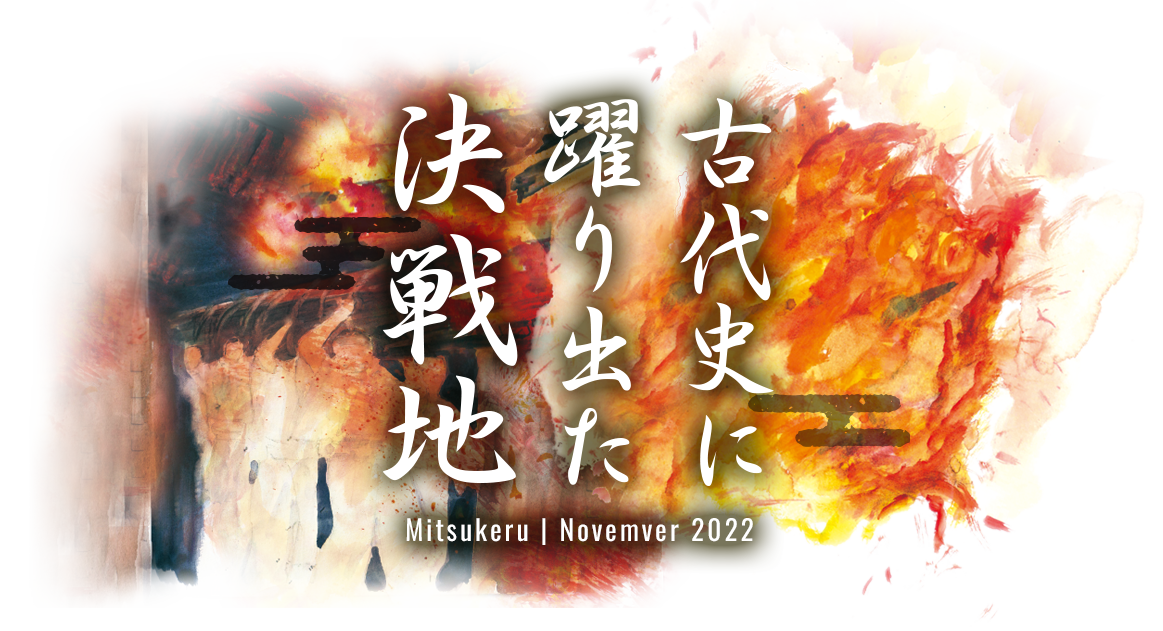


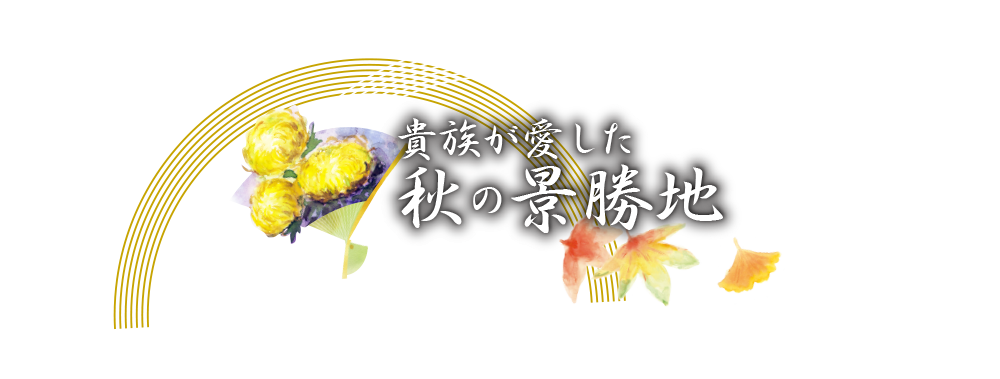
 祝園神社いごもり祭保存会
祝園神社いごもり祭保存会