妊婦のための支援給付について(妊婦支援給付金)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
制度の流れ
- 妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
- 妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
- 出産・産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数x5万円)が支給されます。
- 産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
注意:2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付となります。流産・死産・人工妊娠中絶等により、妊娠が継続できなかった方も、1回目・2回目給付ともに対象となりますので、申請については、母子健康包括支援センター(0774-95-1931)までご連絡ください。
支給対象者
申請時点で精華町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。
注意:他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が精華町に転入された場合は、改めて精華町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
|
|
1回目給付(妊娠届出後) | 2回目給付(胎児の数の届出後) |
|---|---|---|
|
支給額 |
妊婦1人あたり5万円
|
妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む) 注意:流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。 |
|
申請方法 |
申請書を提出 |
申請書を提出 |
|
申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間 |
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間 |
| 注意:申請期限を過ぎると、受付できませんのでご注意ください。 | ||
|
支給時期 |
申請月の翌月末以降 (審査後、決定通知を送付いたします) |
|
| 注意点 | 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。 | |
申請について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦の方が面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請書をお渡しします。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
お子さんの出生後、新生児訪問事業等での面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお渡しします。
(注)妊娠が継続しなかった方は、母子健康包括支援センター(0774-95-1931)までご連絡ください。
手続きの流れ
- 面談時に申請書をお渡ししますので、記入の上、ご提出ください。
- 申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
- 振込口座も、申請者と同一の必要があります。
- 支給時期は、申請月の翌月末以降となります。(審査後、決定通知を送付いたします)
| 1回目給付(妊娠届出後) | 2回目給付(胎児の数の届出後) |
|---|---|
|
振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等の写し) |
| その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等の提出を求めることがあります。 | |
よくあるご質問
Q1:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A1:住民登録のある市町村に申請してください。
注意:出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、母子健康包括支援センター(0774-95-1931)までご連絡ください。
Q2:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A2:経済的支援だけではなく、妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行うため、保健師による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、支援につなげるため、妊婦等包括相談支援事業を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q3:精華町で妊娠・出生届出後に、精華町から他市町村へ転出した場合はどこへ申請したらよいですか?
A3:届出時の住所地ではなく、給付の申請書を提出される時点で住民登録のある市町村へご申請ください。
Q4:精華町に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも精華町で申請できますか?
A4:全国一律の制度のため、同一の理由により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ精華町で申請が可能です。
Q5:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A5:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が、本人名義の口座でしか申請できません。
Q6:申請してからどれくらいで支給されますか?
A6:審査に問題がなければ、申請された月の翌月末以降に振り込みします。
Q7:多胎児を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A7:妊娠届出後(1回目の支給)に妊婦1人につき5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども1人あたり5万円(例:双子の場合:5万円x2人=10万円)を支給します。
Q8:妊娠が継続しなかった(流産・人工妊娠中絶・死産)場合は対象となりますか?
A8:妊娠の届出をし、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数x5万円を申請いただけます。また、妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産・人工妊娠中絶は同様に対象となります。(ただし、妊娠の届出前に流産・人工妊娠中絶をされた方については、医師による胎児の心拍が確認されていた事実及び妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要です。)
Q9:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?
A9:申請内容や口座番号等の確認や支援などで精華町の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。
Q10:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A10:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
妊婦のための支援給付のご案内(こども家庭庁) (PDFファイル: 425.9KB)
注意:このページ内のxは乗算記号を表しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ





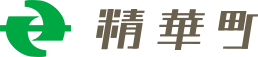


更新日:2023年02月01日